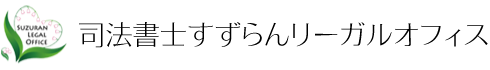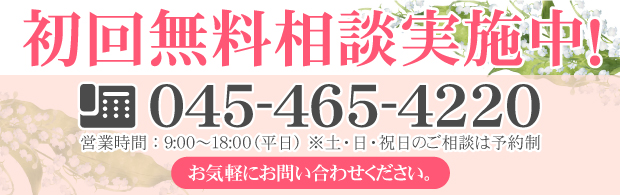平均寿命と認知症

平成25年において、男性の平均寿命は80歳を、女性は86歳を超えたといわれてれています。医療の発展に伴い、今後さらに寿命は伸び、一説によると、平成62(2050)年を超える頃には、男性は 83.5歳、女性は90歳を超えるといわれています。
生命として「生存」する年数が「寿命」であるのに対し、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を「健康寿命」と呼びます。(平成26年版厚生労働白書)。
平成23年の厚生労働省の発表によると、平均寿命と健康寿命との差は男性9.13年、女性12.68年となっています。
この期間は、身体上の問題、意思能力や判断能力の問題など、様々な理由で日常生活が制限される状態となることを意味しています。
これはあくまで「平均値」であり、比較的その期間が短いケース(1年未満~3年程度)から長期(15~20年)の場合にいたるまでの平均となります。
特に高齢者の場合、身体的な障がいから意思判断能力の障がいへと連動する場合も多いので、財産の管理や処分に必要な「判断能力」を有する期間、いわばこの「健康寿命」を念頭に家族信託を設計することが大切です。
「健康寿命から平均寿命」の期間において、個人差はあるものの、意思判断能力を喪失してしまうと、財産の管理や処分といった行為は原則できなくなります。
その最大の原因のひとつが「認知症」です。平成24年時点で65歳以上の高齢者のうち462万人が認知症と認定され、また、その予備軍も400万人と推計されています。合わせて862万人にのぼり(平成27年厚生労働省資料)、高齢者人口の約4分の1となる計算となります。
今後もこの数は増え続けることが予測され、私たちの人生あるいは相続対策を考える際には、この認知症発症というリスクを必ず念頭に置いておく必要があります。
決して遠くない将来、認知症もしくはそれと同じレベルの「判断能力を失った期間」を迎えるとするならば、その期間に、あなたの財産は誰がどのように管理するのでしょうか。
現在、各所で行われている「相続相談」あるいは「相続対策」では、この視点がすっぼりと抜け落ちてしまっています。