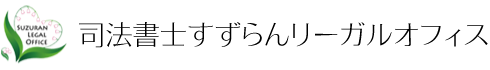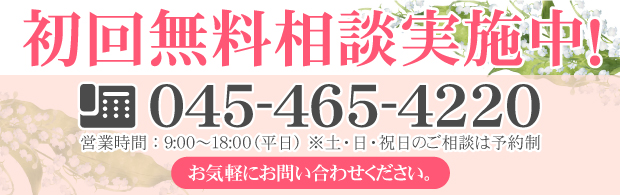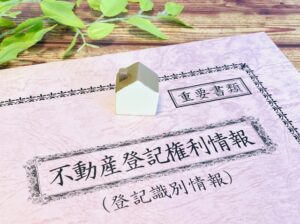家族信託と遺言との違い
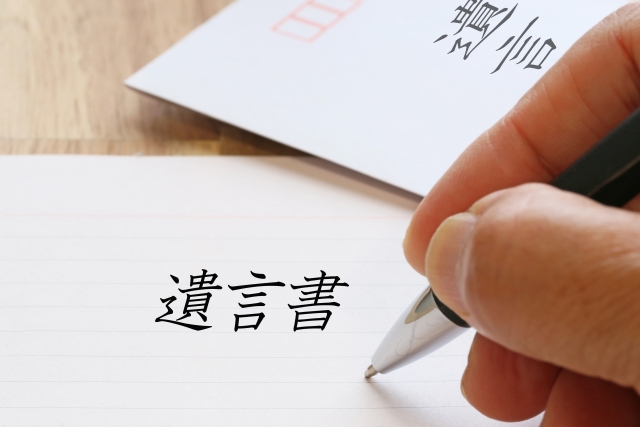
遺言はあくまでも単独行為(自分一人で行う行為)ですので、自分一人で「誰に財産を残すか」を決めることができます。半面、単独行為であるがゆえに、いつでも遺言の書換えや取り消しが可能です。本人が亡くなるまでは効力が発生しないので、何度でも書換えられます。そのため、判断能力が若干低下してきたときに、利害関係人からの圧力で遺言の書換えが他の利害関係人に知られずに行われるリスクも生じます。
これに対し家族信託は「契約で生前の財産の管理とさらに相続発生後の承継先などを受託者に託す」形式ですので、「単独」ではありません。委託者の想いや希望をしっかりと伝えたうえで受託者に託すことができるため、本人が亡くなった際の遺産の分配などについて、家族の理解を得られやすい方法といえます。
また内容の変更に関しても、家族信託あ元気なうちに交わした契約が効力を発揮しますので、もし内容を変更したいのであれば、一般的には受託者との合意の上で変更することになり、勝手には変えにくい仕組みともいえます。
つまり判断能力が低下してきたようなときに、利害関係人からの圧力で遺言内容が恣意的に書換えられるといったことを排除でき、元気なときにクリアな頭で決めた財産管理の資産承継に関する希望を相続発生時まで継続できるという点で、遺言とその役割が異なります。
家族信託で「信託財産として受託者に管理を任せている部分」については、契約書内に「相続が発生した時点で、財産を誰のものとするか」を定めることで、遺言の機能を持たせることができます。従って、機能面でいえば信託の利用と遺言はほぼ同じということはできます。
しかし遺言の場合は、誰に譲るかという「所有権の移転」で終わるため、財産を受け取った人はその財産を自分で管理する必要があります。信託の仕組みで遺言の機能を持たせる場合には、単に財産を譲るだけでなく、その財産については「受託者」という管理者を決めることになります。
例えば高齢の父親が他界し、その財産を高齢の母親に渡そうと思ったときに、通常の遺言だった場合、財産を相続した母親がその時点で認知症を発症していたすれば、相続した財産の管理をするためには成年後見人等が必要になります。
ところが家族信託を使った財産の移転を行えば、単に財産を渡すだけでなく、受益者を母親、管理する受託者w長男にすることで認知症となった母親に代わって、長男が財産管理を行える仕組みを残すことができるのです。